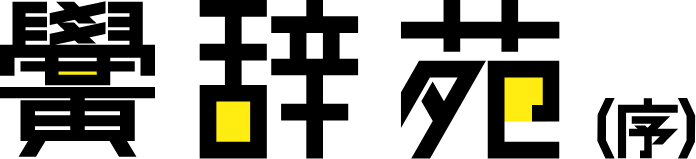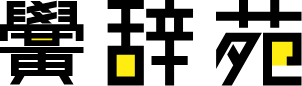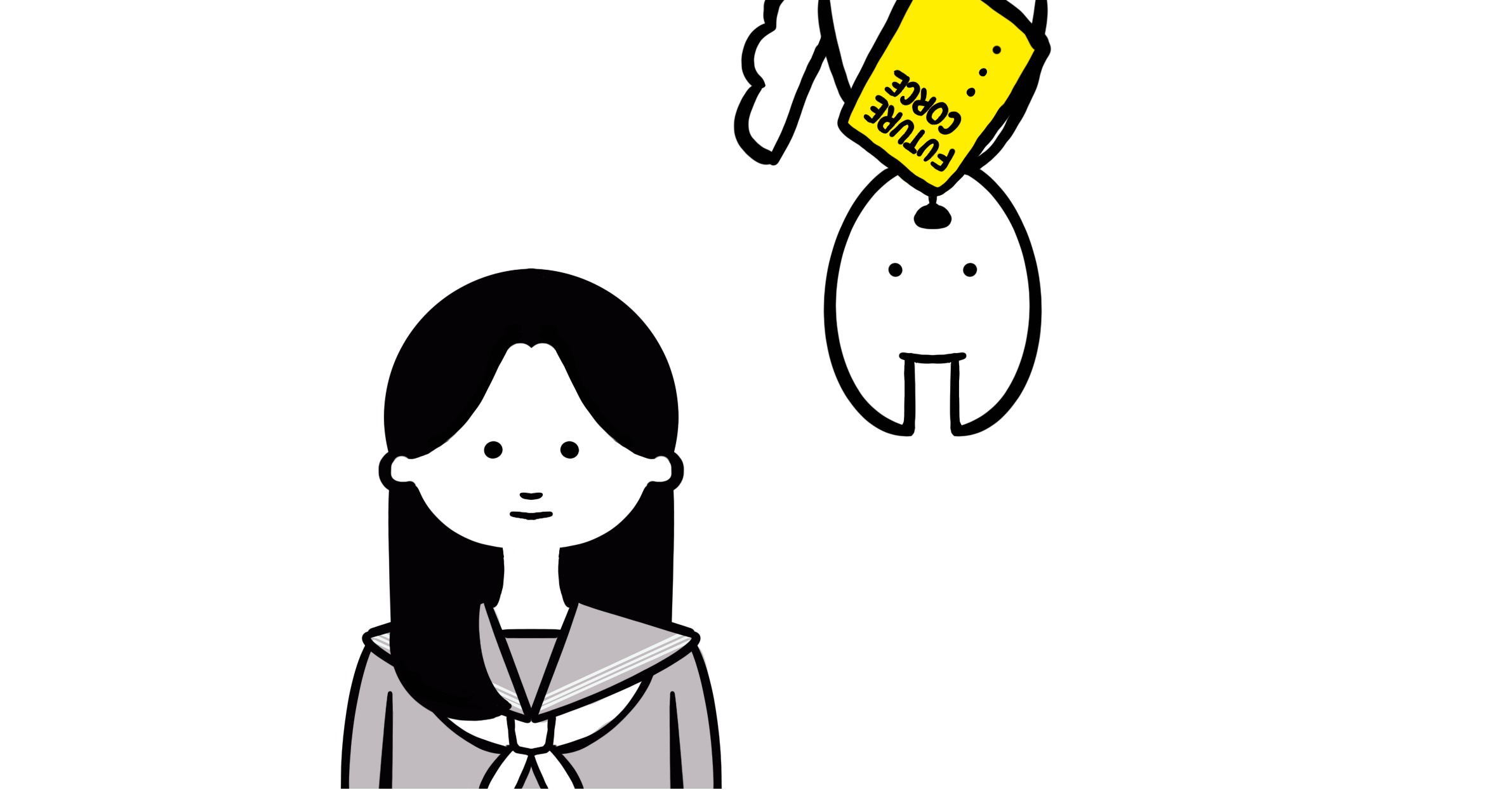CATEGORY
卒業生によるコラム
平成元年卒、1/458。わたしの「VS」ストーリー
2023.02.16
ライター:宮崎 香奈子
イラストレーター:岩間 美咲希
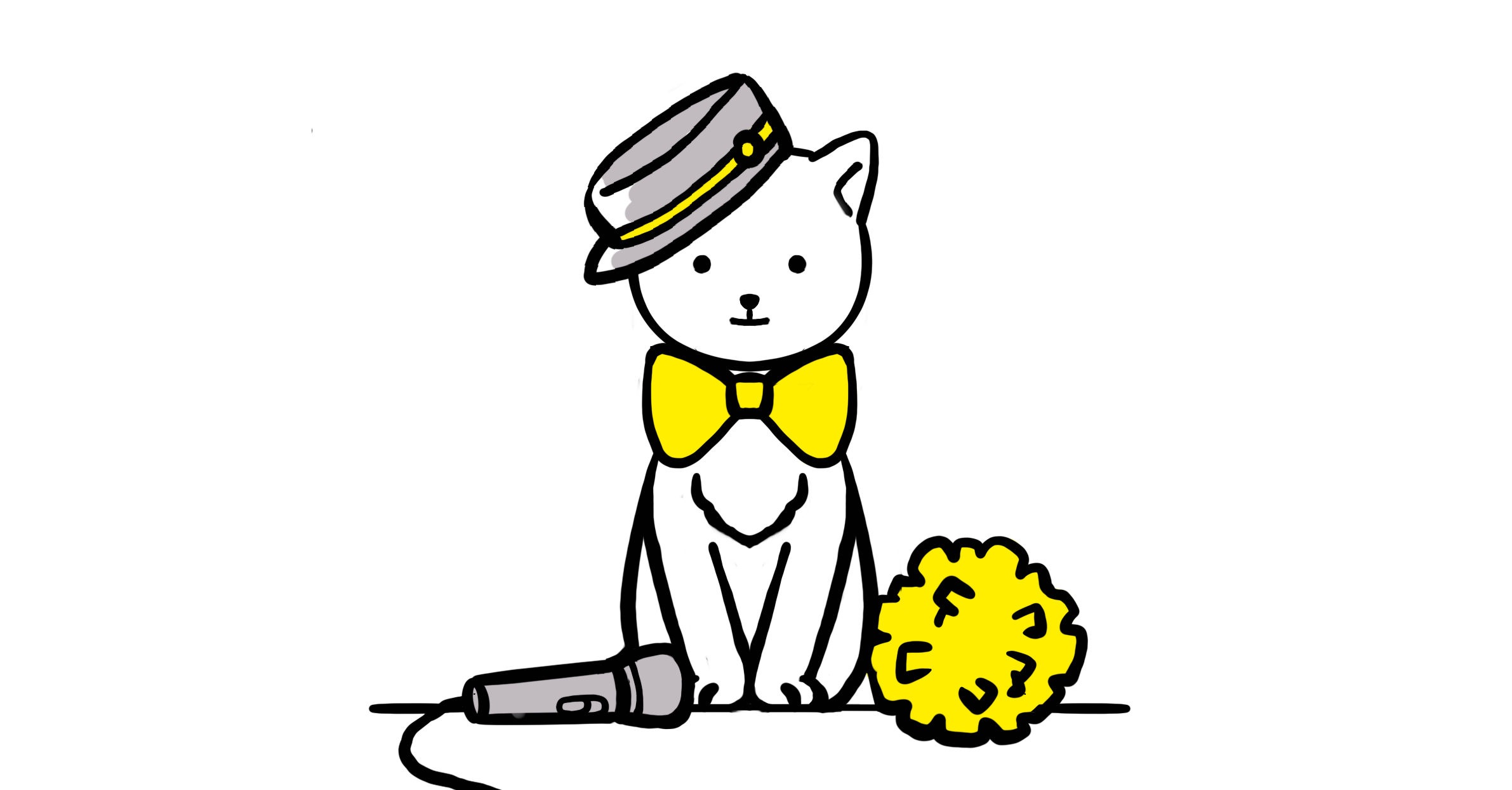
目次
【ナイターVSドリフ】パパとコバカントクとセイセイコー
「カープのコバカントクはね、パパのセイセイコーのどうきゅうせいたい」。
これは、亡き父(1936~2014年、昭和30年卒)がよく発していた言葉だ。記憶は定かではないが、小さいときから繰り返し聞かされていたように思う。だからか、私は高校受験について考える年齢になるずいぶん前から、父が「セイセイコー」という名前の高校を卒業したこと、そして、そこに有名なプロ野球監督がいたことを知っていた(知らされていたというべきか)。
このコラムを読む若い世代のために記させていただくと、小気味よい音で幼い脳に刷り込まれた「コバカントク」とは、広島東洋カープを球団設立初の優勝へ導き、その黄金期を築いた元監督・古葉 竹識(※1)大先輩のことだ。執筆にあたり調べて分かったことだが、広島東洋カープが3度のリーグ優勝を果たした1979年・1980年・1984年に、1971年生まれの私は8歳、9歳、13歳。やはり小学校から中学校まで、父は監督のことを誇らしげに語りつづけていたのである。
しかし当時の私は、プロ野球に一切興味がなく、むしろ父が有無を言わさずチャンネル権を行使する「ナイター」が大嫌いだった。なぜなら、大好きなアニメやドリフの番組を邪魔する「にっくき敵」だったからだ。なので、父の「同級生自慢」が心に響くことはなく、古葉監督の名将ぶりを知ろうともしないまま年月は流れていった。
※1 https://baseball-museum.or.jp/hall-of-famers/hof-128/
【赤青VS黄緑】次女のScrambling Rock’n’Roll
では、なぜ「そんな私が済々黌へ?」なのである。
理由を説明するには、少し生い立ちにふれなければならない。私には2歳ずつ違う姉と弟がいる、つまり「次女」だ。長女と長男、生まれながらにして「長」である姉と弟の間にはさまれて育った私は、いつの頃からか、自分だけが「次」の「女」であることを悔しく思うようになった。「姉のおさがり」を受け取ることや、「男だから」という理由で弟が優遇されることに不満を感じていたし、親の愛情が平等でないとすら考えていた。
今思うと幼稚で恥ずかしく両親に申し訳ないのだが、そんな思いにとらわれていたせいか、小さいときから「決めつけに従う」ことや「普通に倣う」ことを嫌う傾向にあった。例えば小学校で、「男の子は青、女の子は赤が普通」とされることが嫌だった。だから、黄色や緑の上履きを選び、好んで履いていたことを今でもよく覚えている。
しかも多感な年ごろを過ごしたのは、折しも1980年代だ。佐野元春が「つまらない大人にはなりたくない」とガラスのジェネレーション(※2)を代弁し、尾崎豊が「自由って一体何だい?自由になりたくないかい?」(※3)と問い、渡辺美里がマイレボリューション(※4)で「明日を変えよう」と歌い上げていた。にもかかわらず、「女の子は●●しなくていい」と言うことの多かった父とはどんどん折り合いが悪くなり、よりいっそう「決めつけのない自由な世界」に憧れを抱くようになっていった。
※4 https://www.misatowatanabe.com/
【昭和30年卒VS平成元年卒】済々黌に行けば自由になれる!?
そんな中学3年生にとって、済々黌の特徴である「自由な校風」は魅力的だった。また、赤でも青でもなく、黄色がシンボルカラーであることも気に入っており、おのずと「志望校」になったというわけである。しかし両親は「お姉ちゃんと同じ女子高に行けば?」と薦めていたと記憶している。親にしてみれば、姉妹が同じ学校に通えば安心できるという理由だったはずだが、私にとってそれは、またも姉の「次」になることを意味していた。
であれば、それより上を目指し、親を納得させるしかない。積み木くずし(※5)もどきの反抗的な次女が成績だけは落とさず頑張っていたのは、そのためだったように思う。当時、済々黌は姉が通う高校より偏差値が高く、男も女もいる共学であり、さらに父の母校であった。「長」でも「男」でもない私が、「父と同じ高校」に通うことが、父の押し付ける当たり前から自由になる「切符」のようなものだと思い込んでいたのかもしれない。
(しかし、父が亡くなったとき、「単純に父に認めてほしかった。結局は自分が兄弟の中で誰よりも父の背中を追いかけた子どもであった」ということに気がついた。もはや手遅れだが、このコラムを書くために、親子で済々黌について語り合える時間を持てればどれだけ素敵だっただろうと、大いに悔やんでいる)
※5 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%8D%E6%9C%A8%E3%81%8F%E3%81%9A%E3%81%97
【男子3:女子2】ツッパリ女子、自由をはき違えて入学する
さて、である。1986(昭和61)年、春の入学式。
「自由な校風だけん、許されるよね」と、中学時代のよろしくない慣習を見事に引きずっていた私は、式直前に夜なべして制服を「改造」。髪の毛もオキシドールで脱色して登校した(笑)。目立ちたかったというより、ツッパリ少女よろしく「なめられたらいかん」といきがっていた。それでもなぜか先生に怒られた記憶がないのは、自分に都合の悪いことだから忘れているだけなのかもしれない。ただ、とにかく、まわりに「自分みたいな生徒」が少ないことに内心ビックリしたのを覚えている。
もう一つ驚いたのが、女子生徒の数だった。学年458名のうち約5分の3は男子(10組の内ひとつは男子クラス)。100名ほど女子のほうが少ないのだから、私みたいな生徒はやはり悪目立ちする。しかし、その姿で登校しちゃったのだから、もう引くに引けない。私の済々黌ライフは、そんな風に自由の意味をはき違えた状態でスタートしたのである。
その後は普通に(?)友達をつくり、写真部と茶道部にも入って平穏に過ごしていたが、悪目立ちが逆に功を奏したのか、高校2年生のとき運動会の「チア」に選ばれた。チアは3年生を中心に結成されるが、各団、数名ずつ2年生が参加するのが通例となっていた。私は当時流行していたエアロビクスやジャズダンスを学外で習っていたこともあり、踊れることがうれしくて参加。先輩たちにまじって楽しく練習に励んだ。そして、翌年の1988(昭和63)年、高2でチアを経験したという理由もあり、高3の運動会では「青団のチアリーダー」に任命された。
【応援団VSチア】高3の運動会、チア消滅の危機に奔走する
ダンスの楽曲や振付、構成を決め、衣装をパターンから手作りし、他の団に負けないようなチアを「自由に創り上げること」は、0→1のやりがいがある経験だった。またリーダーとして、メンバーを率いる責任について学ぶ機会にもなった。写真部での活動もそうだが、「自分の手から何かが生まれること、表現をカタチにして発表することの面白さ」との出会いでもあったと思う。もしかしたら、クリエイティブな仕事を目指した原点の一つが、ここにあるといえるかもしれない。
しかし、練習を重ねていたある日、ショックな噂話がチアたちの耳に入る。「応援団の男子が今年の運動会にチアは要らんて言いよる」というのだ。急きょ、赤団、白団、黄団、青団のチアリーダーが集まって相談し、男子に確認することに。「誰がそんなこと言いよると?なんでそんなことになると?」。よくよく聞いてみると、一部の間で「男子だけでやりたい」という話が盛り上がり、それが広がったらしい。前述のとおり、当時の男女比は約3:2。彼らに差別意識があったわけではないと思うが、応援団に代表されるキナ線のバンカラは、やはり「男子の世界」と考えられていたように思う。チアは、彼らが思い描く「硬派なイメージに合わない」というのが言い分だった。「またしてもここで、女を理由に区別されるのか」と悔しく思ったのを覚えている。
しかし、チアリーダーも引き下がらなかった。各団の団長たちに掛け合い、女子の思いを伝え、最終的にはチア不要の意向を取り下げてもらうことに成功した。私たちは予定どおり練習を進め、晴れてその成果を運動会で披露することができたのである。この「チア消滅の危機事件」は、いまだに元年卒が集う同窓会や宴会で話題になるエピソードだ。当時を振り返り、「なんで俺たちはあぎゃんこつば言い出したとかね?」と、当事者だった男子も不思議がる。「今になって思うことだけど、当時、もっと済々黌の女子と仲良くすればよかった。でもあのときは、なぜかできんだったとよね」という男子もいて、そういえば私もどこか「男子に対して壁をつくっていた」ことを思い出した。
ちなみに、2022(令和4)年度の済々黌の生徒在籍数は、男子587名・女子639名だそうだ。女子が多い現在の生徒たちにとっては、ピンとこないエピソードかもしれない。男女雇用機会均等法が制定されたのは、私たちが入学する1年前(1985年)のこと。ようやく女性たちが居場所や役割を主張できるようになった、そんな時代であったことは確かなのである。
【世間VS文化祭】あの2人が司会だったイベントが中止に!
運動会に次ぐ花形イベントといえば、秋の「文化祭」だろう。中でも、目玉は「歌の祭典」。多くのアイドルや歌手が活躍し、ザ・ベストテンやレコード大賞、紅白歌合戦などが盛り上がっていた時代だけに、生徒が人気曲を歌ったり踊ったりして、面白おかしく演出するステージコンテンツだ。舞台上に立つのは、翌春に卒業を控えた3年生。そして、それを進行する司会に選ばれていたのが、有田くんと上田くん、つまり後の「くりぃむしちゅー※6」だった。コンビ結成前の彼らが取り組むことになっていた、運命的な「初ステージ」。これは同級生の間では有名な話だが、残念ながら彼らのプロフィールに記載はない。なぜか?それは、このステージが「実現しなかった」からだ。
1988(昭和63)年9月、昭和天皇のご容体の悪化が日本中に伝えられた。これにより、私たちにとって最後となる文化祭のメインステージも「自粛のため中止」を余儀なくされた。当時、私は、その舞台で「少年隊」を披露する予定だった男子に頼まれ、衣装係を担っていた。縁の下の力持ちとして、キラキラブルーのサテン生地を街まで友達と買いに行き、採寸し、かっこよく作ろうと意気込んでいた。そんな中、学校側から発表された中止は、準備を進めていた多く生徒たちを激しく落胆させたのである。
中には、決定を静かに受け止めることができず、直談判のため校長室へ乗り込んだ生徒もいた。最近になって、直談判した男子たちのおぼろげな記憶をつなぎあわせた話によれば、「すでにリハーサルまで進んどったと思うとよね。だけん、みんな納得できんかった。それで、結構な人数で校長室まで押しかけたとよ。なんでダメなのか、どうにかして実施できないのか強く訴えたばってん、歌の祭典の場合は派手というか、面白くするためにふざける内容というか……。それで、許可はできんて言われたと思う」。
※6 https://naturaleight.co.jp/cream/
【自分VS自分】たたかおう!自分らしさに出会うために
こうして、日本中が自粛ムードに包まれる中、“世間の空気に挑んだ我らのたたかい”は全く勝ち目なく通り過ぎた。そして、翌年の1989(昭和64)年1月7日、昭和は幕を閉じ、どこか釈然としない思いを抱えたまま、平成元年を迎えたのである。
大学受験のとき、私の父は相も変わらず「女の子は県外に出なくていい。熊本の国公立に行きなさい。もし落ちても女の子に浪人はさせない」という腹立たしいルールを敷いた。結果的に第一志望の受験に失敗した私は、第二志望の大学に入学し、その大きな挫折が原因でしばらく腐って過ごしていた。しかし2年になって「このままではダメだ」と考え直し、チアのときにそうだったように、自分の得意を活かす活動をしたり、新しいサークルをゼロから立ち上げたりして、新たな前進を始めたのである。そして、そういった活動の一つひとつが、現在の仕事への道筋をつくり、今なお活かされている。
若さとは未熟さであり、未熟ゆえに自分の姿は見えにくく、叶いそうもない強い相手や大きな相手とたたかおうと無茶をする。その相手は、あるときは兄弟や友達、親や教師であり、あるときは勉強や部活であり、あるときは世の常識や偏見のようなものだ。しかし大概は、自分自身とたたかっているに過ぎない。喜んだり、感動したり、悔しがったり、苛立ったり、途方に暮れたりしながら、自分自身をのぞき込み、その姿を知るようになるのだ。私にとって済々黌は、中学時代に想像していたような「決めつけのない自由な場所」ではなかった。けれど、移り変わる時代のなかで自由や責任について考え、様々な経験を通じて、自分らしさと出会う機会を与えてくれたことに感謝している。
追記:ちなみに、あのとき司会をするはずだった2人がとんでもない人気者になったことが、抜け落ちた文化祭の思い出のピースを埋めてくれた気がしている。彼らのプロフィールにはない「歌の祭典」は、あのとき、リハーサル場所にいた生徒たちだけのプレミアムステージになった。私にとって彼らは、いつまでも自慢し続けたい、父にとってのコバカントクのような存在だ。
※今回の執筆にあたり、集まって当時の思い出話をしてくれた同級生(松田くん、泉くん、吉田くん、富加見くん、槇尾くん、蓮尾くん、けいちゃん)、そして記事に登場することを許可してくれた、有田くん、上田くん、みなさんに感謝!
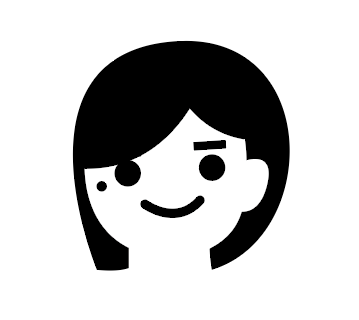
宮崎 香奈子Kanako Miyazaki
1989(平成元)年、熊本県立済々黌高等学校卒業。熊本女子大学卒業後、有限会社ウルトラハウスに入社し、タウン情報誌全盛時代の「タンクマ」編集に携わる。また、編集部時代に、「海砂利水魚(現・くりぃむしちゅー)」の連載コーナーを企画、担当。退職後、フリーランスのライター・イラストレーターを経て、熊本から福岡へ。「株式会社利助オフィス」にて、主に広告冊子のディレクションおよび編集に従事。2019年、自治体に特化した様々なサービスを展開する「株式会社ホープ」へ転職。ヒントとアイデアを提供する行政マガジン「ジチタイワークス」の編集長として奮闘中。https://jichitai.works/

イラストレーター
岩間 美咲希iwama misaki
2013(平成25)年 熊本県立済々黌高等学校卒業。熊本大学教育学部中学校教員養成課程美術科を卒業後、教育委員会での勤務を経て2023(令和5)年NHK入局。現在名古屋放送局視聴者リレーションセンターにて従事。
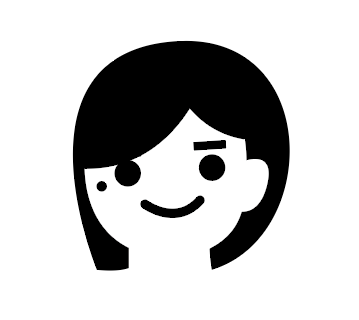
宮崎 香奈子Kanako Miyazaki
1989(平成元)年、熊本県立済々黌高等学校卒業。熊本女子大学卒業後、有限会社ウルトラハウスに入社し、タウン情報誌全盛時代の「タンクマ」編集に携わる。また、編集部時代に、「海砂利水魚(現・くりぃむしちゅー)」の連載コーナーを企画、担当。退職後、フリーランスのライター・イラストレーターを経て、熊本から福岡へ。「株式会社利助オフィス」にて、主に広告冊子のディレクションおよび編集に従事。2019年、自治体に特化した様々なサービスを展開する「株式会社ホープ」へ転職。ヒントとアイデアを提供する行政マガジン「ジチタイワークス」の編集長として奮闘中。https://jichitai.works/

イラストレーター
岩間 美咲希iwama misaki
2013(平成25)年 熊本県立済々黌高等学校卒業。熊本大学教育学部中学校教員養成課程美術科を卒業後、教育委員会での勤務を経て2023(令和5)年NHK入局。現在名古屋放送局視聴者リレーションセンターにて従事。
140th anniversary special column
140周年特別記念寄稿
Column by graduate